NHK-FM「アニソン・アカデミー」のMC・中川翔子氏は自身の好きなアニソンについて語る際、時として「一文字萌え」という様式を用いる。
この真似をして、クラシック音楽で同じような感じのことをやってみようという企画です。
2015年1月24日放送「アニソン・アカデミー」より:
TARAKO『ナゾナゾ 夢の国』について、「一文字萌え」の手法で熱く語る中川翔子さん
いきなり関係ないですが、当方ホームページにて「『アニソン・アカデミー』は昭和のアニソンをどのように伝えたか」というページを展開しておりますが、こんなふうに文字起こししてるくらいなら、↑こーゆーふーに音声をそのまま上げた方が早いだろ!ということに気づいた(笑)。
ま、今はそんな話をする場所ではない。
クラシック音楽における「一文字萌え」ならぬ「1音萌え」を、特定の「演奏」から探ってみたいと思います。「曲」としてどの演奏にも萌えるのではなく、この演奏のこの1音に萌える、ということです。ここがクラシック音楽の特別なところ。演奏によってまるで違ってくるから。
それで、普通なら出来上がってからこのブログも公開するのでしょうが、作ったり直したりしながら公開してゆきます(笑)。
てか、持ちネタがそんなにないから、作りながらネタを探していこうということです。
先行きまったく不透明ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
◆チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」第2楽章
この曲はカラヤン指揮ベルリン・フィルの演奏で聴き覚えた。1976年録音のバージョンです。
誰の演奏で聴くかは重要である、ともう分かってる年頃でしたが、カラヤンなら間違いないだろう、ぐらいの気持ちで選んだような記憶があります。(話途中ですが、私の文章は「です・ます調」と「である調」が混在します。ご了承ください。)

(LP再生装置も家にあったが、ヘッドホンで聴きたいものはカセットテープで買ってラジカセで聴いていた。この曲はヘッドホンで聴きたかったんですね。)
カラヤンは生涯7回、「悲愴」交響曲を録音してますが、そのうちの6回目となります。
この演奏による第2楽章のこの箇所よ、この箇所:
もちろんこれで良い。誰も文句がつけられない。この演奏で十分である。
だが、歳月が経過し、「カラヤンじゃない」指揮者の方に関心が移って久しくなった頃、この曲のあまりにも魅力的な演奏に出くわすこととなる。
同じカラヤンによる1971年の録音。遡ること5回目のものです。(オケも同じくベルリン・フィル)
この赤丸の音!
音楽を抱きしめるような歌わせ方。ガーンときた。この箇所にこんな表情を与えるとは!音楽の底知れなさを思い知らされる瞬間でした。
でも人によっては、カラヤンのこーゆーところが嫌なんだよ、という人もいるかもしれない。その気持ちも分からないでもないです(笑)。
どんな表情を加えるかは曲によるのだ(当たり前だけど)。メロディーの中からどういった感情をすくい上げ、演奏に込めるのか・・。ロマンティックな解釈で、この場合は正解。音楽に溺れちまった者が勝ちよ。
「1音萌え」ってこういうことでいいのかな。
ちなみに、カラヤン最後の7回目の「悲愴」の録音は1984年。(オケはウィーン・フィル)
いい感じで軽やかだ。こっちの方が好きだという意見もあるだろう。「枯れてきている」「熟成」なんていう言葉も当てはまるのかな??
◆ブラームス:交響曲第1番 第4楽章と第2楽章
ラジカセを買う前、私は東芝EMIの「ニュー・セラフィム・ベスト100(後に150)」というシリーズによりクラシック音楽の世界に飛び込んでいった。LP1枚が1300円と安く、入門用としてうってつけでした。
そうすると自動的に、ブラームスの交響曲はバルビローリ指揮ウィーン・フィルで聴くこととなった。

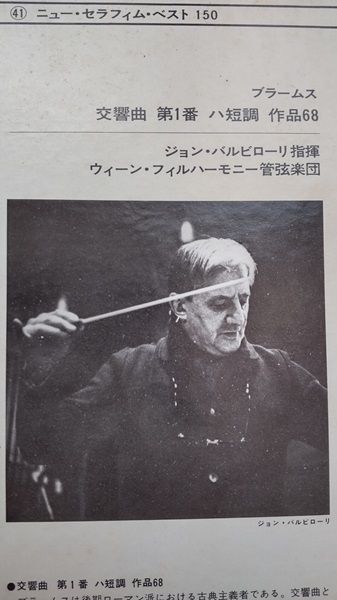
サー・ジョン・バルビローリ
本ブログは原体験について語るものではありませんが、やはり最初に出会う演奏って大事だと思う。その演奏がその曲の「標準」となってしまうのだから。その意味で、最初のブラームスがバルビローリだったってのは大げさに言えば一つの奇跡のようなものだと思っている。今でもCDで持っていて、クセのないブラームス(?)を聴きたい時は食指が動きます。
で、このレコードにより初めてブラームスの第1番を聴いていた人なら誰もが経験したことだと信じて疑わないことがあって。
第4楽章の弦のピチカートの箇所。音が2つに分かれてしまってる。ところが、この演奏を正しいものだと思い込んでしまったのだ。
4分音符ではなく、16分音符2コみたいなふーに思っちゃっていたわけです。
なものだから、正しい演奏を聴いた時はびっくりしちゃったわけよ。(俺だけかな?)
正しい演奏の例:
んで「正しい演奏」に慣れるまで時間がかかったわけよ。
というか、若干こじつけですが、今でも「正しい演奏」の方に違和感がある(笑)。音が2つに分かれてる方に親しみを覚える。多少キズのある方が愛着が持てるから、ということでもない。ピチカートは完全には揃っていない方が温かみがあるのだ。←説得力ねーなー
実は、第2楽章にも同じことが起きていて。
やはりピチカートの箇所。
バルビローリの演奏:
ちゃんとした再生装置じゃないと分かりにくいということに今気づきましたが(笑)、やはり音が2つに分かれてしまってるんです。第4楽章ほど明確じゃないし、そんなに気にはならないけど。
この箇所も、正しい演奏だと当然、音が揃ってるわけですよ。
正しい演奏の例:
バーンスタインって基本、縦の線は揃える人だから。(大概の指揮者はそうです)
でもこの箇所も、多少ズレてる方が味わいが深まると考えるのはこじつけが過ぎるだろうか?
少なくともブラームスの交響曲第1番の場合、ピチカートの粒が完全に合ってしまうと必要以上に冷徹な感じがするように思う。ブラームスが考えてたのはそんな音楽じゃない気がする。
例えば、カラヤンの1983年の録音だと、同音のアルペジオみたいにポロンと響かせてるのよ。意図的にこんなことできるのかな。
同音のアルペジオ風(?)
第4楽章でも。完全には揃えてない。微妙にずらしてる。さすがカラヤンなんじゃない?
偶然の産物かなあ。
てか分かりづらいよね!ちゃんとしたスピーカーで聴かないと。
今、自分でパソコンで再生してるんだけど、こんなに分かりにくいと思わなかった(笑)。
◆ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」第4楽章
それでは分かりやすいものを。
例の、シンバルが1回だけシャーンと鳴る箇所。
スメターチェク指揮プラハ放送交響楽団の演奏がとにかくすごい。
普通は弱ーく「シャーン」と鳴らすのだが、思い切り「バシャーン」と鳴らすの。初めて聴いた時はぶったまげた。
ドリフのコントかよ
ところが譜面をよく見ると、この音はメゾフォルテとなっている!(しかも、わざわざ「Solo」とまで書かれている。)この演奏で正しいのだ。
ではなぜ、普通は弱くたたいてるのだろう。
おそらくドヴォルザークは、夕暮れ迫る田舎町に遠くからお寺の鐘が「ゴ~ン」と鳴るような感じが欲しかったのだと思う。
次に来るクラリネットの黄昏感を出す前段としての雰囲気づくりのために。
ちょうど、チャイコフスキー「悲愴」の第4楽章のタムタムのような効果を狙ったんじゃないかなあ。
(やっぱ分かりにくいですが、銅鑼が「もわーん」と鳴ってます)
だとすればメゾフォルテなんかで鳴らせない。どうしても打点の瞬間の音が際立ってしまう。そこはドヴォルザークの計算違いだったのではあるまいか。
はっきり言って銅鑼そのものの響きが頭の中にあったのではないかと思う。シンバルじゃなくて。
せめて、合わせシンバルじゃなく大きめの吊りシンバルを用いるべきのような気もしますが・・。
この考え方からすると理想的なシンバルの音が、オットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団の演奏の中にあります。
打点音はせず、もわ~んとした音が持続する。そもそも、だから音符にスラーが付いてるのだ。このクレンペラーのシンバルの使い方はいいねえ。
(ただ、テンポが遅いからなおさらそーゆーニュアンスになってるという点も否めない。もちっと早めのテンポが欲しい。)
と、と、と、思ってたんだけど、スメターチェクの演奏に聴き慣れてしまうと、以上の仮説は根底から覆される。
「夕暮れ感の演出」などとは全く違うのではないかという気になってくるのだ。そんなのと関係なく、「音楽の区切り」として普通にシンバルを使ってるだけ。なのかもしれない。
ひとしきり終楽章が盛り上がりましたが、さあこのあと素晴らしいクラリネットソロが始まりますよ、ご注目!と聴衆の注意を引き寄せるためのシンバルのような気がしてくる。
んなわけねーだろ、とツッコミたいが、「聴き慣れる」とは恐ろしい、その演奏が必然のものになってきて本当に分からなくなってくる。
普通に音楽を賑わすための、パレード感みたいなのを出すためのシンバルだったりして。(こんなことは世界中でもう語り尽くされているのだろうか。。?)
時々、鳴ってんだか鳴ってないんだか本当に弱々しく「シャン」と打点音だけする演奏があったりするけど。
誰の演奏とは言わないが:
こんなマッチを擦ってるようなよく分からないシンバルよりは、はるかにスメターチェクのは意義があると思う。
シンバルだけじゃない。とにかくスメターチェクの「新世界より」は個性的すぎて、あちこち変なのよ。おかしいのよ。スリル満点だわ。
てか本当は、曲自体が変なのよ。ドヴォルザークの交響曲第9番って超名曲だけど、おかしな点がいっぱいあるのよ。例えば、(以下略)
◆ベートーヴェン:交響曲第7番第4楽章
前の項でオットー・クレンペラーのテンポについて触れましたが、基本的に遅い人で。
私はどちらかといえば普通に快速なのが好きなので、クレンペラーを敬遠したくなることが時々あります。
で、交響曲第7番よ。クレンペラー遅い。
まずは普通の演奏から。カルロス・クライバー指揮ウィーン・フィル。
少し速すぎる方かもしれないが、このくらいで良いという人は多いだろう。なにしろクライバーだぜ。
この演奏と比較するのも露骨だが、同じ個所がクレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団だとこうなる。
1960年、クレンペラー75歳時の録音。
いや、いいんじゃないの。これはこれで。
赤丸の箇所の木管の響きが好きなのよ。雄大で壮大で冒険的でスリリングで前向きでポジティブで、なおかつ哀愁とクライマックス感があるから。
このテンポだからこそ醸し出される味だと思う。
宇野功芳先生もこの演奏を推していた。「誰よりも遅いテンポを少しも動かさず、リズムをじっくりと踏みしめつつ最後まで進む。」「立派さにおいては比類がない。」(『交響曲の名曲・名盤』講談社現代新書)
ところが。
ファンはもうよくご存じでしょうが、こともあろうにクレンペラーはさらにもっと遅い演奏を残している。
1968年にニュー・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した録音です。
この短い箇所だけ聴いたのでは違いが分かりにくいが、楽章全体の演奏時間が前の録音より17秒ほど長い。それだけ遅いのだ。
(ちなみにクライバーはダル・セーニョもきちんと行っているので、楽章全体の長さはクレンペラーと同じぐらいになってます。)
いやーどうだろうか。晩年っぽさがにじみ出ている?クレンペラーはこのとき83歳ぐらいでした。
いくらなんでも遅すぎるということで、この盤の評判はあまりよくないようです。
だが。だがだがだが。
テンポが前より遅くなってるのに、赤丸の箇所は静かな高揚感を増し、さらなる高みへと昇っているようではないか。
まるでこの1音のために、このテンポを採用してる感じさえする。正に1音萌え。
バカボンのパパみたいに「これでいいのだ」という気持ちになってくる。
80歳代の境地を居ながらにして体験できる、とも言えるのではないかな。
捨てたもんじゃない演奏です。
◆ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」第1幕
カルロス・クライバーが出てきたので、その関連を。
オペラなので、指揮者の個性というより歌手の技量で大きく左右されるんでしょうけど。
取り上げるのは、「トリスタンとイゾルデ」第1幕第2場の末尾、クルヴェナールが演説をぶつ箇所です。
比較のためにまず、カール・ベームによるバイロイト音楽祭でのライブから。
クルヴェナール役はエーベルハルト・ヴェヒター。
ワーグナーの楽劇にベームじゃ何か物足りないんじゃないかという先入観が、正直私はありました。(しかも《トリスタン》だし。)
いや、でもバイロイトなんですよやっぱり(笑)。音楽の宇宙が既に構築されてるのね。
誰も割って入れない。世界がもう出来上がってしまってる。
時代が少し進むと、重々しさだけではない新しい感覚の演奏が出てきて。
まずはバーンスタインの盤。クルヴェナール役はベルント・ヴァイクル。
先ほど書いた通り歌手のカラーによって印象がガラリと変わってくるから比較もへったくれもないんだけど、それにしたって全然違う。
特に、独唱よりもその後の合唱の部分(笑)。この箇所を聴き比べるのも面白いから今回わざと入れています。
でも、ここで着目したいのは赤丸の「Hei!」の1音なのである。
バーンスタイン盤と同じ頃、カルロス・クライバーの盤が出た。クルヴェナール役はディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ!!
あたしゃ「Hei!」でひっくり返ったわけよ。
当時、バーンスタイン盤とクライバー盤は甲乙つけがたい、どちらも名盤と言われてたんだけど、あたしゃこの「Hei!」のただ1音でクライバーに軍配を上げたわ(笑)。こっちの方が面白いじゃん。
さすがフィッシャー=ディースカウ、いい仕事するねえ。
いやーオペラの解釈もどんどん新しくなって、楽しくなってきてるよね。
しかし、昔の演奏、例えばカール・ベーム盤などよりさかのぼってフルトヴェングラー盤などで聴くと、やっぱ味があるのよ。
なんと!クルヴェナール役は、こちらもフィッシャー=ディースカウ!!!
録音時期はクライバー盤より30年ほども前になります。
いいねえ、昔の演奏。実に良い。風格が違うわ。これぞワーグナーの神髄って感じがするじゃん。そりゃそうだ、新しい時代より古い時代の方がワーグナーの時代に近いんだもの。
そりゃ迫真性も相対的に高くもなろう。やーオペラは深いねえ。
てか、オペラというか声楽の方にまで手を広げてしまうと、みんなそれぞれ個性があるから差別化することの意味が縮まってしまう。というか、本当に「一文字萌え」になっちゃうし。
器楽中心でいきたいと思います。
◆ビゼー:歌劇「カルメン」第2幕
とか言いながらオペラなんだけど。
オペラの「伴奏」ね。
非常にベタですが、「闘牛士の歌」のイントロの出だしの1音についてです。
1963年のカラヤン指揮による演奏:
これよ、これこれ。
この「音を引っぱる」感じ。これぞ「1音萌え」の真骨頂ですよね。
でもこれはあくまでオペラの中の1曲に過ぎないので、もっとこの1音を堪能するのは、「闘牛士の歌」の前の合唱から続けて聴かなければならない。
みんなが闘牛士をもてはやすから、闘牛士は歌い出すのだ。
例:
これよ。これこれ。
「さあ闘牛士、何かやってくれ」というリクエストに応えて歌い出すわけね。
だから、期待を込めた一瞬の間がなければならないし、「なんとこれから歌を歌うんですぜ!」という意外性と興奮の高まりを表現するためにイントロ最初の1音は十分に引っぱらなければならないのです。
カラヤンが1982年に録音した演奏。これぐらいは音を伸ばしてほしいよね。
ああ良いんじゃないの。
ただ、さっきの1963年のもそうなんだけど、カラヤンの場合「闘牛士の歌」全体のテンポが少し重いんですよね。
そこで登場するのが1964年のジョルジュ・プレートル指揮の録音ですよ。マリア・カラスがカルメン役を務めたことで有名な盤。
これよ、これこれ。
音の引っぱり方としては、おそらくカラヤンと同じぐらいなんだろうけど、問題はその後のテンポよ。テンポというか「ノリ」よ。すごく軽快。
軽快だからこそ最初の1音の引っぱり加減がなおさら生きてくる。輝いてくる。要は対比よ。対比が重要なんだわ。
オペラの全曲盤としてはところどころクセの強い箇所のある演奏らしくて、もしかしたらこの箇所も「クセの強い」部類に入るのかもしれませんが、プレートルってこんな感じなんでしょ?←無責任
このイントロに限っていえばこれぐらいやってほしい。てか、「オペラ」ならこれぐらいやってもらわないと面白くないですよね、きっと。
◆ドヴォルザーク:チェロ協奏曲第3楽章
ということで「音を引っぱる」話です。
協奏曲で独奏の細かい点に触れだしたらキリがありません。
伴奏に着目します。
第3楽章の最初のチェロ独奏が終わった後のこの箇所。
例として上げるのは、ジョージ・セル指揮ベルリン・フィルの演奏です。(ちなみにチェロはピエール・フルニエでした。)
セルだし、ベルリン・フィルだし、何も文句はない。
ポイントは赤丸の4分音符。テヌートもアクセントもスタッカートも何もついてないこの音符をどう奏でるかによって、だいぶニュアンスが変わってきます。
私はここで「引っぱる」という言葉を使いたい(笑)。うんと引っぱってほしいの。
とはいえ全体のテンポが鈍重では意味がない。
カラヤン指揮ベルリンフィルの例。(ちなみにチェロはロストロポーヴィチです。)
なんかねっとり系のカラヤンで、この部分はあまり好きではない。(協奏曲全体としては悪い演奏じゃないと思います。)
ジャクリーヌ・デュプレ&バレンボイム指揮シカゴ響の演奏も同傾向です。
こういうのじゃなくて、「引っぱる」感じですわ。
好きなのは、やはりなんといっても小澤征爾指揮ボストン交響楽団の演奏。
これはラジオから録音したもので、1984年のザルツブルク音楽祭でヨー=ヨー・マと共演したものです。
そうか、この部分はこーゆーふーに演奏するのか!と当時あたしゃ感動したものです。
小節への入り方の間合いを計った上で、伸びやかに豊かでふっくらと弾んだ4分音符をキメている。引っぱっている(笑)。
しかも(しかもですよ)、2つめの4分音符の方を余計に引っぱっているの。すごくないですか。
まあ、音符1つ1つをどう奏でるかというよりも、この場合は小節に入る際の「間合いの取り方」の問題かもしれないけど。そっちの方が重要かもしれませんが。。
◆モーツァルト:交響曲第40番第4楽章
さて、「間合い」といえば思い出されるのは、モーツァルトの交響曲第40番第4楽章です。
この曲も最初は「ニュー・セラフィム・ベスト150」で聴き覚えました。
今にして思えば、チャールズ・マッケラスの演奏だったんですねえ。。

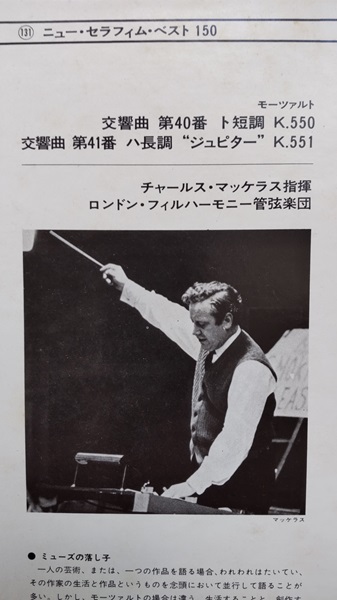
サー・チャールズ・マッケラス
今レコードプレーヤーがないので音はお示しできませんが、大きくハメを外すような箇所はなかったと記憶してます。
ここで取り上げるのは、第4楽章の展開部の入口の箇所はところ。
「間合い」というより「タメ」の話になるかもしれませんが。
まずは例として、ブルーノ・ワルターが1952年にウィーン・フィルを振ったもの。(第1楽章でのポルタメントが有名なやつです。)
提示部の流れのまま展開部へ入っていく。マッケラスの演奏も、確かこんな感じだったと思います。
こういう感じが私には「標準」となったので、展開部の入口でテンポをぐっと落とす演奏に接したときは、やはりド肝を抜かれたものです。ああこんなやり方があるのかと。
当然、逆の人も多いでしょう。テンポを落とすのが普通だと思ってたら、インテンポのまま突き進んでいって驚いた、みたいな。
ここをどう演奏するか。
テンポを落とすだけならまだ単純で。
フルトヴェングラーは微妙にリタルダンドしていくのである。
最後の赤丸の音。深い意味を持たせようとしてるように聴こえる。一旦音楽をリセットして展開部に入っていくような感じ?
提示部が非常に快速だったからなおさらインパクトがある。フルトヴェングラーらしい音の揺らし方であり音楽の捉え方だ。聴き慣れてしまえば、これが必然になる。こうじゃない演奏では物足りなくなってくる。なんでもそうですが。。
ところが、フランス・ブリュッヘン指揮18世紀オーケストラの演奏になると、意味合いがさらに変わってくる。
フルトヴェングラーと違う1音にポイントを置いてくるのだ。
赤丸で音楽が一度立ち止まる。(なので、本当はその後の休符に丸をつけるべきかもしれません。)
こうなるとちょっとした事件である。何が起きてるのか考える必要が生じる。音楽が底なしの迷宮の中に入っていくようだ。ここまで深く掘り下げる必要が果たしてあるのだろうか、という気にさえなってくる(笑)。モーツァルトって、こんなことまで考えたんだろうか(笑)。
古楽器系の「斬新な解釈」ってちょっと苦手で、音楽のストーリー性が辻褄合わなくなったら意味ないと思っている。
この1箇所だけ見れば個性的で面白くても、全体の物語から見てどう映るかだ。物語が破綻してしまっていては、いくら部分部分が良くてもダメだと思う。
このブリュッヘンはどうなんだろう。いやー私には分からない。崩し過ぎているとまでは言えないような気もするが、この崩し方に意味があるのかが分からない。ストーリーが読み解けていないのよ。
絶対音楽なんだから意味なんかなくていーんだよ、という意見が出るであろう。そういう意味の「意味」じゃなくて。
もし過度な表情であるなら、むしろつけないでほしいんだよね。ただ、余計な表情なのかどうかが、まだよく分かってないのよ。
そんなようなもんだから、あたしゃモーツァルトの40番が聴きたい時は、バーンスタイン&ウィーン・フィルを選ぶようになっている。
さらっと流れていくような感じがいいの。
小林秀雄の書いた「かなしさは疾走する。」っていう意味は、「テンポをいじらない」っていう意味も含まれているんだと勝手に思ってみたり。。
(この楽章については、展開部~再現部のリピートを行うかどうかという着眼点もあるのですが、それについては当方ホームページの「ソナタ形式はそんなにすごいのか」を是非ご覧ください!)←宣伝
◆シベリウス:交響曲第3番第1楽章
ホームページといえば、当方ホームページにはシベリウスの交響曲について書いたものもありますので是非ご覧ください。
ちなみにこれは、シベリウスの交響曲と漫画「ワンピース」を絡めたつもりのハズでしたが大失敗に終わったものです(笑)。
この中に交響曲第3番の第1楽章の主題について触れたページがあって。
「1音萌え」に相応しいので、同じネタをまたやらせてください。
それほど有名な曲じゃないので知らないという人も多いかもしれませんが、非常に親しみやすい曲で、私は大好きです。
第1楽章の提示部がこんな感じ。サイモン・ラトル指揮バーミンガム市交響楽団の例です。
これが再現部ではこうなる。
同じメロディーである。
なのに、8分音符の旗のつなげ方の違いもさることながら、再現部の方は赤丸の音符にアクセントがついていないのである。
なぜだー!!というネタでした。
分かりやすくするため、テンポの遅い演奏でもう一度確認します。
ジョン・バルビローリ指揮ハレ管弦楽団によるものです。
まず提示部:
つづいて再現部:
演奏の仕方を譜面通りに変えているように聴こえます。
シベリウスはどういう意図で書き分けたのでしょうか?
答えは私などには分からないけど、ヒントとなるのが、パーヴォ・ベルグルンド指揮ヨーロッパ室内管弦楽団の演奏にあると思う。
提示部:
再現部:
そうですね、提示部の時点で既に軽快ですが、再現部ではさらに軽やかになっている。颯爽としている感じ。
赤丸の1音はさりげなく通り過ぎてしまい、あまりにもそっけなく聴こえるほど。
でも、そこがいい。1音萌え(笑)。
ベルグルンドはシベリウスの交響曲全集を3回録音していて、ヨーロッパ室内管弦楽団とのものはその3回目なんだけど、1回目2回目は提示部と再現部の描き分けが微妙な感じなんだよね。
1度目の全集より(オケはボーンマス交響楽団)。
提示部:
再現部:
2度目の全集より(オケはヘルシンキ・フィル)。
提示部:
再現部:
「微妙」というより、こうして並べて聴くと、3度目の全集での線のクリアさが際立っているのが分かる。ベルグルンドが室内管弦楽団を用いた理由は正にそこにある。「明晰さ」最優先で小編成のオーケストラを起用したそうだ。なるほどねえ。
てか、話が細かすぎるよね(笑)。
やっぱり分かりにくい方向に行っちまったか、、
◆ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番第4楽章
では、せっかくだからもっと細かいものを。
室内楽だと声楽同様、奏者の個性的なものが比重を占めることになるんで、ちょっと扱いにくいんだけど、ものすごく好きな1音があって。
4分音符の和音だけで表情がグラデーションのように変化していくこの箇所。
例として東京クヮルテットによる演奏:
この、チェロの赤丸の音なんだけど(笑)。
普通なら誰も気にも留めない1音だろうが、1970年にスメタナ四重奏団が録音した演奏だと、このようになる。
これが絶品なんだわ。
上品なグリッサンドがつく。実にセクシー。単純な音の配列の中、一番低い声部がいきなり生き生きとした存在感を示す。こうなるともうこの演奏が必然になってくる。聴くたびこの1音に集中してしまう。
実際には次の音と合わせて「2音萌え」ととらえるべきなのかもしれないが。
てか、下降の音型でスラーがついてりゃグリッサンドがつくのはむしろ自然で、全然珍しいことではないかもしれないけど。
同じスメタナ四重奏団が1984年に録音したものだと、このグリッサンドが控え目になってしまう。
いや、これぐらいでいいんだよ。と思う人も多いかもしれないが、ここは大げさにやってほしい。誰もがハッとするぐらいに。
バーンスタインがウィーン・フィルと弦楽合奏版でやった録音も私の愛聴盤ですが、もっと大胆に表情をつけてもよかったんじゃないかと思ってます。
まあ「1音萌え」っていうと、結局、ポルタメントとかグリッサンドとかチョーキング(笑)とかが施されてるものが主流になっちまうのかなあ。。
◆ブルックナー:交響曲第4番第1楽章
最後にとっておきの1音を。
この曲はずっとカール・ベーム指揮ウィーン・フィルの盤で聴いてきて、もうこの演奏で十分だと思っていた。
展開部の頂点の金管によるコラール:
提示部の悠然とした第1主題と同じリズムでありながら、さらに超然とした表情で我々の前に立ちはだかり、ただただ圧倒させる。我々はひれ伏すしかない。でも恐れ多いからではなく、感謝の気持ちからひれ伏すのだ。(←何言ってんの?)
こんな音楽はなかなかない。
この演奏でずっと満足してたんだけど、ジュゼッペ・シノーポリ指揮ドレスデン国立管弦楽団の演奏と出会う。
たしか吉田秀和のラジオの番組「名曲のたのしみ」に、月に一度「私の試聴室」があり、そこで取り上げられたのだった。
私も感動してしまったわけよ。特にこの箇所に。
もはや表情などなく、何の作為もなく「無表情」であるかのように響く。そうなんだよなあ、大自然だから表情などは無用なんですね。我々はただ唖然としてればよい(笑)。
宇野功芳先生はクナッパーツブッシュ/ウィーン・フィルによるブルックナーの交響曲第3番を評して、「《楽器の音》がまったくしない」と褒め讃えていたが、同じ表現が当てはまるかもしれない。
タンギングも人間の息遣いも、金属が振動する感じも出してはならない。あたかも自然音のように鳴り渡らなければならないのだ。
この演奏のこの部分にあまりにも惹かれてしまい、シノーポリの盤じゃないともうこの交響曲は聴けなくなってしまったわ(笑)。
何の作為もない1音にこそ「1音萌え」の神髄があるのかもしれませんねえ。。
というか、この箇所は「1音」ではなく「ワンフレーズ」として捉えるべきかも。。。
つづく(?)